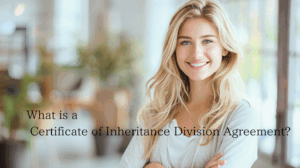死因贈与とは?
死因贈与という言葉を聞いたことがあるでしょうか。読んで字のごとく、死を原因として発生する贈与のことです。民法554条では、「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与」と表現されています。死因贈与は、遺贈と非常によく似ています。遺贈も人の死亡によって財産が特定の人に与えられます。死因贈与と遺贈とではどのような違いがあるのでしょうか。
死因贈与は、あくまでも贈与の一種なので、民法549条にある通り、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じます。つまり、あげる側である贈与者と、もらう側である受贈者の双方の合意によって、成立します。まず、贈与者が生きている間に、受贈者との間で、自分が亡くなったら、特定の財産をあげますという贈与契約を締結しておきます。そして、実際に贈与者が亡くなった際に、受贈者は契約通りにその財産を取得します。
これに対して、遺贈は、契約ではなく、遺言によって財産を譲ります。あげる側である遺贈者は、生きている間に、遺言をのこしておき、遺贈者が亡くなった際には、遺言通りに、もらう側である受遺者に財産が渡るようにします。ただ、遺贈は遺言によって遺贈者の一方的な意思表示をすればよいので、いざ遺贈者が亡くなったときに、受遺者は放棄することもでき、確実に遺贈者の意思が実現できるとは限りません。
2024年4月より、不動産においては、相続登記の義務化が始まりました。相続登記、そして遺贈による登記もこの義務化の対象に入っていますが、死因贈与は入っていません。不動産の死因贈与の場合、死因贈与契約を締結した際に、贈与者の生前に仮登記という登記を入れておき、将来贈与者が亡くなった時に、本登記を入れるのがいいでしょう。仮登記を入れておくことで、自分の権利を保全しておくことができます。
自分が死んだときに財産を特定の人に渡したいと考える場合、大抵の人は「遺言書を書こう」と思うでしょう。遺言書の場合、死ぬまで自分以外の人たちにその内容を秘密にすることができることはメリットかもしれませんが、受遺者が放棄してしまい、自分の意思を実現できない可能性もあります。そこで、遺贈ではなく、死因贈与という方法を使ってみるのもいいでしょう。死因贈与契約を締結することで、確実に自分の与えたい人に財産を渡すことができるでしょう。